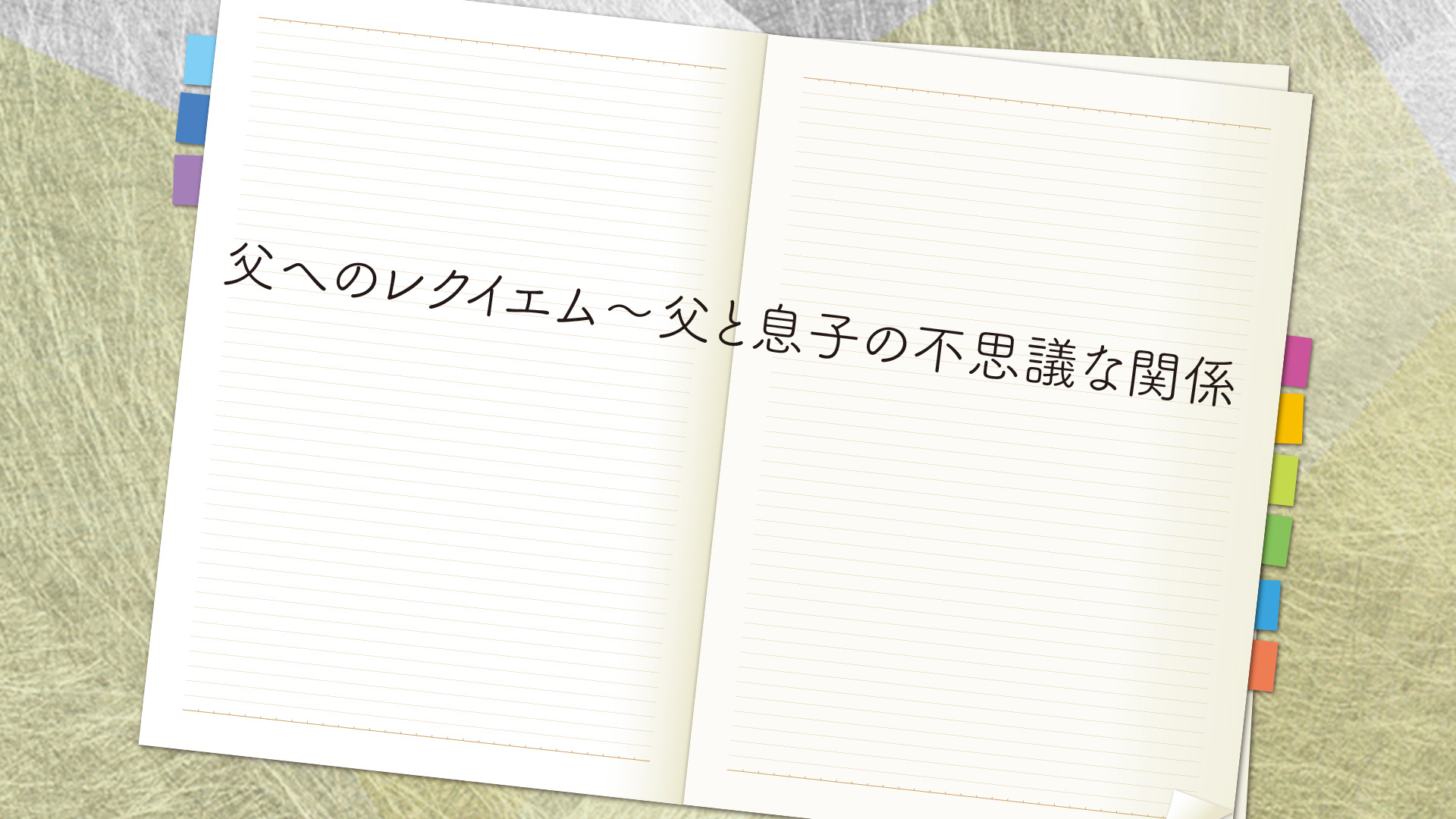
第一章・父と息子の不思議な関係
はじめに
今年、6月24日深夜に父が亡くなりました。
91才でした。
母が亡くなったのは2001年なので、18年もの長きに渡る後追いでした。
どなたも興味があるとは思えない内容とは思いながら、世の中の大半の方に理解してもらえないであろう「私の父と息子の不思議な関係」を父へのレクイエムとして、ここに記録したいと思います。
書き出すと、なかなかにハショることが難しくなり、いくつかに分けた長編になりますが、よかったら読み物としてご一読ください。
私自身は、この数年、遡れば約20年間は、途中途中、こちらの精神力、体力、経済を奪うと感じたこの父を、正直、重荷とも感じたり、だけど優しさも強さも情けなさも他愛なさも含めて「私の唯一のパパ」であったり。
哀しみ、憎々しさ、愛しさ、やるせなさ、あらゆる複雑な気持ちを抱えながら、弱った父と甲斐甲斐しく世話をする息子の関係が終わるイメージも持てず、「いつか失う現実」に対して、深く掘り下げたりはせずに、半ば淡々と接してきた私です。
順番だからいつか亡くなる、それを哀しく感じていたのは、実は父がまだまだ元気だった70代の頃まででした。
80代になると哀しく感じる前に単純な覚悟となり、逆にいつまでも生きている気がして覚悟は薄れ、もっと言うならば、覚悟を必要としない地点に来ていました。
父は私のヒーローでもあった人、育ててくれた人、そして血縁家族に対しての愛情は厚く、仮に家族側が間違っていても理不尽であっても、家族の外敵と感じるものから護ろうとする人。
その愛情は偏愛でもあり、時にエゴイズムにも感じ、それを重たく感じた時、そもそも愛そのものがエゴイズムなものだという結論に達したりもしました。
父は口数は少なく物静かで、社会的に登り行った頃は逆らえない絶対的ボスでもあったけど、恐ろしいくらいに取り繕いができず真っ直ぐ過ぎる子供じみた面があり、その天然さは人に思いやりを持てないように見えたり、我が儘が過ぎると感じたり、あまりに邪気のない真っ直ぐさは可愛げでもあるし、小賢しい嘘つきではない信頼感はあったけど、トータル的にみると、人間的に好みではないと感じたものでした。
人間性云々など超越して、とりあえず、とにかく、家族は絶対的な繋がりだとする人もあるけれど、それは親から子に向けての「生んだ責任、護るべき者」という感覚だけであり、家族って、選んだのではないお仕着せの人間関係であるということを思ったりもしたこともあります。
ともかく、父は私にいろいろと考えさせられた人物でもあったわけです。
最期まで全身全霊で父を看たのは息子
父を最期まで全身全霊ともいえる渾身の力で看取ったのは息子です。
父は最期まで息子に甘え、息子は父の最期まで、できる限りを尽くし、側についていました。
私は最期辺りは、息子の精神力の限りが来ないように、努めて補佐をしている状態でした。
55才差の親友同士
息子は1983年、父が55才の時に生まれました。
この時から36年と2ヶ月半、父はほぼ、常に息子と一緒でした。
私が父と暮らしたのは22年、しかも物心ついてからは最も多忙な時期の父だったし、高校を卒業してからの私は自由な学生生活を謳歌し(厳密には学校以外で)家にそうそう居ることのない娘だったので、息子は娘の私より長きに渡り、父と密度の高い共生をしていたことになります。
加えて、私が父と暮らした頃には母が居たので、父だけと深く関わるというより、いわば一般的な家庭の父と娘でした。
母が亡くなって一人になった父と息子の18年間は特に密な共生だったと考えられます。
※別の章に経緯を書きますが、生まれてから22才までの息子は母である私宅を中心にセカンドハウスとして父宅にも部屋を持っていました。
父はどういった作為をしてでも、できるだけ息子を手元に置いていたかったのです。
息子が幼い頃、仕事を持つ私は息子を父(厳密には父母)に預けるというより、不必要な時も父が息子をかっさらって行ったという方が正しくもあるのです。
息子にはこの二重生活になんの不思議も感じていなかったそうです。
父と息子の同居そのものが始まったのは2005年頃、約4年の父と息子の蜜月を経て、2009年に息子が結婚しても2011年に長女が生まれても、息子は父と同居し続けました。
世間から見れば、本来は娘の私が父と暮らすべきなので、「あんたはずいぶん楽ね。」などと揶揄されながらも、私は「そうなんよ~。」と笑い飛ばしてはいました。
しかし、私が拒んだのではなく、父には息子と居ることが当たり前で、息子も父と居ることが当たり前という、彼らの意思でした。
息子に「平気なの?」と聞いたら「俺、おじいちゃんが居るのが当たり前やねん。」と。
私もまた、この二人を別々に切り離す気にもなりませんでした。※
血縁にも相性とか相互バランスがあるのでしょう。
理解不能とも感じつつ、父と息子は、私から見れば世代を超越した一心同体に近かったのです。
息子は赤ん坊から成長していったわけで、普通の男子ゆえにもちろん15才も過ぎると自分の世界も広がり、当たり前にも「おじいちゃん」とは少し距離ができます。
けど、父は息子を、息子は父を常に気にしていたのを私は感じていました。
いわば、元から不思議な糸で繋がっているような二人でした。
赤ん坊が大人になり、大人が年を取って赤ちゃん返りして、この二人は何年もの間に自然と逆転しながら連れ添っていました。
お互い長年の知己、もはや、忖度的な遠慮も嘘もない長年の親友のような。
私の中の父の遺言
弱っていく父が、まだ普通に会話できていた昨年の夏に言った言葉は忘れられません。
「よく○○(息子)を生んでくれたな。どうもありがとう。」
これは私の中で、父の遺言になりました。
7年くらい前から息子には爪を切ってもらい、食事の世話をしてもらい、お風呂にも入れてもらう(デイサービスをイヤがった)、果ては下の世話もしてもらいながらも、アレはイヤだコレはイヤだの我が儘の限りを言い尽くす。
けど、私が手伝おうとしても、息子にしてもらうから要らないと言う。
最初は娘の私が何もしていないような罪悪感や違和感があったけど、様子を見ていると息子が世話をしていることが自然になっていて、私は気にしなくなりました。
この時、つくづく、彼らは他が介在できない関係性だと感じたのです。
そして、
「息子を生んでくれてありがとう」
の言葉によって、ああ、この人は(普通じゃしてくれないことをしてくれる)孫の存在を当たり前に所有物化していると感じていたけど、そうではなかったこと、ちゃんと感謝していることが分かったことが嬉しく。
そしてそれは私のたった一つの、だけど父にとって最高の親孝行になったのかも知れないと感じました。
私は父の最高の人生の伴侶、親友を生んだのだと思えて、必然とか偶然とか運命とか宿命とか、全く分からないけど、何かの組み合わせやタイミングでなるべくしてなったソレ。
息子の中ではまだ側に居る父
しかし逆を思えば、おじいちゃんという人生の伴侶、親友を亡くした息子の喪失感は計り知れません。
息子にも予測できたこと、心構えていたこと、だけど彼はネガティブにならない性分。
どれだけ父が弱っても、医師が諦めてくれと言っても、基本的に私と同じポジティブシンキング全開なまま、どうしたらまた元気を取り戻すのか、どうしたらまだまだ生きていられるかだけを真剣に考えていただけに、本人自身もびっくりするくらいガックリしていました。
どう振る舞おうが、常にやるせない哀しみを背負って数ヶ月。
それまで身近にあった遺骨をお墓に納骨した途端、暗いお墓に戸惑った父が寂しくて息子の名を呼んでいるのかと思ったほどに、数日間、高熱にうなされた息子。
12月の父の誕生日には仏壇にケーキを供えていた息子。
彼の中では父はまだ側に居るのでしょう。
第二章・息子に生かされ生きた父の尊厳
末期の父の情けなさを受け止められなかった私と自然に受け止めていた息子
私自身は、父の死を心で整理がつかずとも、形としてはすんなり受け止めました。
もはや、生きていることが可哀想な状態でもあったからです。
私には、弱って我が儘しか言わない父、いつも読んでいた新聞に目を通すこともなくなり、食事もおぼつかず、排泄も不自由になり、果ては「せん妄」という精神疾患になってしまっては、すでに私の中にある父とはかけ離れました。
息子に尋ねたことがあります。
「お母さんにとって、おじいちゃんはもともとヒーローパパやってん。だから今のおじいちゃんを受け止められないねん。あのパパが?っていう情けなさとか哀しさとか痛さとか。あんたはどうして普通に受け止められるの?」
息子は言いました。
「ずっと一緒に居て、徐々に今になったやろ?俺にはそれも自然で普通やねん。俺が面倒かけてきて年月が経って、今度は俺がおじいちゃんの面倒を見る番になったってだけやねん。」
そんなものなのか?
私が非現実的な幻想追い人で、息子は現実的な事実受け止め人なのか。
そしてこんなことも言っていました。
「俺は生きてきて、どんな時もいつもお母さんとおじいちゃんが側に居た。離れている時も俺の中ではずっと側に居た。俺は新しく家族を持ったけど、気持ち的に俺の家族はお母さんとおじいちゃんやねん。年数の問題やろか?絆みたいなもんやろか?」
うーん。
祖父祖母は早くに他界していたし、とっとと親から離れてマイワールドを謳歌した私には分からない感覚なのです。
人間の尊厳とはなんなのかを自問自答した
春。
父が蕎麦が食べたいというので作ってから、ベッドから足を下ろし、腰を支えて身体を起こす。
あまり食べられない。
初夏。
最期の方は、水を口に持っていっても飲めない。
ストローでも吸う力がない。
吸い口で与えても溜飲力がない。
可哀想だし疲れるし、だけど可哀想だし、私はとうとう泣きたくなり、「なんでこうなっちゃった」と思う。
他にも様々な、もっと壮絶なことが沢山あり、私はヒーローパパであった人を前に情けなく痛く、人間の尊厳とはなんだろう?デクになっても生かすことが尊厳ならば、一体何が尊厳ではないのだ?
と、自問自答していました。
遡れば、多分に昨年末には寿命だったのだろう。
息子はあらゆる手を尽くして生かせた。
そう、息子が生かし続けた。
ある時は、なんであの子はこんなデク人形になっても父を生かすのか、こうも生かし続けたのかと、残酷じゃないかと泣けてきました。
けど、私が亡くなった父の顔を見て、最初に口をついて出た言葉は、自分でも想像できないものでした。
「パパ、頑張ったね。」
そして
「○○(息子)とまだまだ生きたかったから頑張ってたんだね。」
ここで私は、父は尊厳を保って生き続けていたのだと感じることができました。
第三章・「私のパパ」はずっと以前に消失したと思わずには立てなかっただけ
私の中ではすでに消失していた「パパ」
しかし厳密にいうと、私の中で父、「私のパパ」を失ったのは、もっとずっと以前です。
私は不思議と、幼い頃に常に抱っこされていた父の温もりの記憶はあるのに、それは印象としては淡い淡い水彩画でしかなく、私にとっての「パパ」は、私が14才頃から華々しく威光を放った父であり、どこに行っても「立派なお父様ですね。」と言われた堂々たる強い油絵の父なので、(未だに本当の理由は分からないが)全てに近いほどにほぼ全てを失った状態で73才で退職し、経済的な面(ほぼ、地震で再建と大きな修繕をした内容に於いてです)で40才の私に頼ってきた時、「私のパパ」は背中でガラガラと音がして消失していました。
甘ったれ根性を自覚したとき
背中のガラガラという音は、「パパの消失」と共に「支え、後ろ楯のない私」を知った音でもありました。
支えや後ろ楯という言葉はただのアカンタレな発言ですが、いわば、私にとっては、幼い頃からヒーローだったパパゆえ、ヒーローを失くしたという意味です。
それまでも自立心の塊のような私は、間接的には援助をしてくれていても、露骨な援助を求めたことは全くなかったので、育ててもらったことも含めると経済的なお返しをするだけで、状態に変わりはないじゃないか、と思うものの、無鉄砲極まりなく自由奔放に生きていたのは、心の奥に潜在する「帰る砦=父」という甘えた心があったからであることを初めて強く自覚しました。
結局は自立していようが、しょせん甘ったれた嬢でしかなかった私のこの恐怖感を話せる唯一の母は病の最中だったので話せないまま。
父への「お返し」のために仕事のオファーを受けるだけ受けて忙し過ぎたのもあるけれど、見舞うと話してしまいそうなのが怖くて避けていたのもあり、私は母をあまり看てあげられず、それについては今でも悔いています。
母が元気なら心頼りたかった。
それより、亡くなるのを知っていたのに少しも側に居てあげられなかった。
私は重油のような思いを抱えながら、ひたすら一人で恐怖感に抗っていました。
だから私は過去に既に一度、「パパ」を失くしていると感じていました。
そう思いたかった、そう思うことで「甘ったれた後ろ盾」を潔く諦めたかったのだと思います。
「パパ」は消失していなかったと悟った
ところが。
亡くなって14時間後に私の「パパ」は消失していなかったことを悟ります。
父が亡くなっても職場にすら告げず(時間縛りでないからどうにでも調整できるゆえ)、亡くなった当日は抜けると迷惑がかかる大事な打ち合わせだけツラッとこなして帰途につきました。
職場だけでなく、誰かにリアルタイムで「父が亡くなった」というようなネガティブ報告をしても、報告された側は言葉に困るでしょう。
私は別に何かを言って欲しくもないし、相手を困らせたくもなく、深刻であればあるほどに在り来たりな返事に在り来たりな返事をすることすら煩わしい。
良くないことだとは思うけど、私は言葉の非力さを肯定してもいるし、現実を知る由のない人と居る方が笑っていられるし、饒舌なくせに実際は誰にも何も話していないことが多いのです。
若い時に
「私がよく喋る時は本心を隠すため」と言ったことがありますが、今もそのままなのです。
どんなことも、まずは時をかけて自身で整理、消化したい。
奥歯を噛みしめて、イヤというほどに手で顔を覆いながら、定まっていく一つの場所をせめて温めようともがき、そうして心でばかり計り続けたものが冷静な言葉に生まれ変わるまで。
けど、この時、まだついぞさっきのレアな帰途なのに、あまりに壮絶だった数ヶ月間、連絡一つしなかった大切な友人には聞いて欲しくてたまらなくなり、電話をしました。
彼は電話に出たなり、
「お父さん、何かあったの?」と。
どうして分かったのかは分からない。
だから余計、私は唐突に素直に答えました。
「パパ、死んじゃった。」
ふだんなら
「父が亡くなった。」という言葉を使うのに、この時は、聞き慣れた彼の声に父の末期や亡くなった時を経てやっとホッとして、父、というよそよそしさや礼儀は超越して、
「パパ、死んじゃった。」という言葉になりました。
「パパ」は消失したと思いたかった頃以来、私はどんなに親しい人にも「パパ」という名称を使わなくなっていることを自覚していました。
イイ年なんだから当たり前、とかではなく。
強く立っていられるよう、よそよそしく「父」と呼ぶことで、甘えていられた「パパ」が消失していることにしていたかったのです。
なのに素直で居られる友人にすんなり「パパ」と言ったこの時、やっと気付きました。
「私のパパはずっとパパだった。消失なんかしていなかった。ずっとパパは居た。」
に続く






